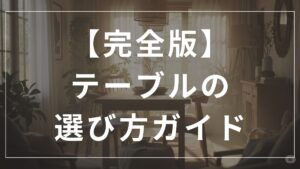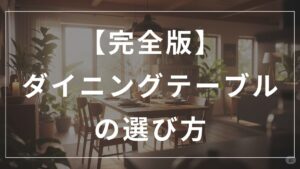ダイニングテーブルを選ぶ際、「大きい方がいい」というアドバイスをよく耳にしますが、その選択が本当にあなたの暮らしに合っているのでしょうか。
実は、ダイニングテーブルが大きすぎることが原因で後悔するケースは少なくありません。失敗ブログなどでは、「180cmは大きすぎた」「160cmでも圧迫感が…」といった声や、人気のウォールナット素材を選んで後悔したという体験談も見られます。
一方で、小さいテーブルを選んで後悔するパターンもあり、理想的なサイズは一体どれくらいなのか迷ってしまいますよね。
この記事では、ダイニングテーブルが大きいことで生じる後悔の具体的な失敗例から、メリット・デメリット、そして大きなダイニングテーブルのある家を実現するために、おすすめできる人・おすすめできない人の特徴までを徹底解説します。
150cmは大きいのか狭いのか、といった具体的なサイズ感の悩みにもお答えしながら、後悔しないための最適な一台を見つけるお手伝いをします。
- 大きいダイニングテーブルで後悔する具体的な理由
- サイズや素材選びでよくある失敗例
- 家族構成や部屋の広さに合った理想的なサイズの選び方
- 購入前に確認すべき重要なチェックポイント
ダイニングテーブルが大きいと後悔する理由
- 失敗ブログに学ぶリアルな体験談
- 180cmは大きすぎたという失敗例
- 160cmも大きすぎたというケース
- ウォールナット素材で後悔する点
- 逆に小さいサイズを後悔をするパターンも
失敗ブログに学ぶリアルな体験談

ダイニングテーブルのサイズ選びで失敗した方々の体験談には、これから購入を検討する上で非常に参考になる教訓が含まれています。
特に多く見られるのが、部屋の広さや生活動線を深く考えずに「大は小を兼ねる」という言葉を信じ、大きいサイズを選んでしまったというケースです。
実際に設置してみると、「部屋全体に常に圧迫感があり、視覚的に狭く感じるようになった」「テーブルの周りの動線が致命的に狭く、キッチンへの移動や配膳のたびにストレスを感じる」という声が多数挙がっています。
特に、椅子を引いた状態でのスペースや、食事中に人が後ろを通るための通路幅(最低でも60cm以上、理想は100cm)を計算に入れていなかったことが、後悔の大きな原因となっています。
また、テーブルが大きすぎると日々のメンテナンスも大きな負担になります。
重量があるため一人では簡単に動かせず、テーブル下の掃除機がけが行き届かなくなったり、食べこぼしが溜まりやすくなったりします。
さらに、広い天板を毎日拭き上げる作業も、想像以上に手間がかかるという点も、日々の小さなストレスとして挙げられていました。
「友人を招いた時のことばかり考えて大きいテーブルを選んだけど、普段の生活を考えると完全にオーバースペックだった…」というリアルな声は、デザインや憧れだけでなく、9割以上を占める「普段の暮らし」での使い勝手を最優先にイメージすることの重要性を教えてくれます。
180cmは大きすぎたという失敗例

幅180cmのダイニングテーブルは、一般的に6人掛けとして利用される、ゆとりある広々としたサイズです。
来客が多いご家庭や、二世帯住宅、家族でゆったりと食事や作業をしたいという理由で選ばれることが多いですが、このサイズならではの具体的な失敗例も存在します。
最も大きな問題点は、前述の通りスペースの確保です。十分な広さ(目安としてLDKで20畳以上)のリビングダイニングでない限り、180cmのテーブルは空間の大部分を占めてしまいます。
これにより、ソファや収納家具といった他の家具の配置が著しく制限されたり、くつろぎの空間であるはずのリビングが窮屈に感じられたりすることがあります。
さらに、日常的に使用する人数が少ない場合、広すぎる天板が逆にコミュニケーションを阻害することさえあります。
例えば、家族4人で使用する場合、向かいに座る人との物理的な距離が遠くなり、自然な会話がしづらくなったり、中央に置いた大皿料理に手が届かず、その都度立ち上がらなければならなかったりするというデメリットが生まれます。
天板の中央部分がデッドスペースになりがちで、食事以外の作業スペースとして活用できるメリットはありますが、主な用途が家族の食事や団らんである場合、持て余してしまう可能性が高いサイズと言えるでしょう。
180cmテーブルを検討する際の絶対条件
このサイズを検討する場合は、設置スペースの寸法をメジャーで正確に測るだけでなく、新聞紙などを広げて実寸のイメージを確認することが不可欠です。
その上で、テーブルの全周に最低でも80cm〜100cm程度の通路兼作業スペースが確保できるかを必ず確認してください。このスペースが確保できない場合、日常生活に大きな支障をきたす可能性が非常に高くなります。

160cmも大きすぎたというケース

幅160cmのテーブルは、4人家族がゆったりと使えるサイズとして非常に人気があります。
「標準的な150cmでは少し物足りないかもしれない」「来客時にもう少し余裕が欲しい」と考え、少し大きめの160cmを選ぶ方は多いです。
しかし、この「あと少し」のわずか10cmの違いが、日々の使い勝手に大きな影響を与え、後悔につながるケースも少なくありません。
特に、12〜15畳程度の平均的なリビングダイニングに設置した場合、160cmのテーブルは思った以上の存在感を放ちます。
普段、椅子をしまっている状態では問題なくても、食事のために全員が椅子を引いた状態では、背後の壁やキッチンカウンターとの間が非常に狭くなり、人が通れなくなるといった事態が発生しがちです。
家族が食事中に席を立とうとすると、他の人に一度椅子を引いてもらわないといけない、といった不便さが日常的に起こり得ます。
また、テーブルが大きいことで、部屋全体のインテリアバランスが崩れてしまうことも深刻な問題です。
空間に対してテーブルだけが過度に大きく目立ってしまい、他の家具との調和が取れず、どこか落ち着かない空間になってしまったという失敗談も見受けられます。
日常の使い勝手と空間全体のバランスを考えると、「少し余裕を持たせる」つもりが「少し大きすぎた」という結果になりやすいのが、160cmというサイズの難しさであり、慎重な検討が必要な理由です。


ウォールナット素材で後悔する点

ウォールナットは、チークやマホガニーと並び世界三大銘木の一つに数えられる高級木材です。その深く美しい色合いと重厚感から、ダイニングテーブルの素材として絶大な人気を誇ります。
しかし、その優れた特徴ゆえに理解しておくべき点や、後悔につながる可能性もいくつか存在します。
部屋全体の印象が暗くなる・重くなる
ウォールナットの最大の魅力であるダークな色味は、お部屋のテイストや環境によっては「渋すぎた」「思ったより部屋が暗く重たい印象になった」と感じられることがあります。
特に、床材や建具、他の家具も濃い色で統一している場合や、窓が少なく自然光が入りにくい部屋では、空間全体に圧迫感が出てしまう可能性があります。
モダンで落ち着いた雰囲気を演出する一方、ナチュラルで明るい空間を好む方には不向きな場合があります。
ホコリや傷が目立ちやすい
色が濃い木材の宿命として、白いホコリや繊維、そして明るい色の傷が非常に目立ちやすいというデメリットがあります。
こまめに掃除をしないと、すぐに天板に積もったホコリが気になってしまうため、手入れの頻度は増えるかもしれません。小さなお子様がいるご家庭では、カトラリーによる傷が白く残りやすい点も注意が必要です。
価格と材質の問題
ウォールナットは高級木材であるため、他の木材に比べて価格が高くなる傾向があります。特に、中まで全てウォールナットで作られた「無垢材」のテーブルは高価になります。
予算を抑えるために、基材の表面に薄くスライスしたウォールナットを貼り付けた「突板(つきいた)」を選ぶ方法もありますが、無垢材ならではの質感や経年変化の風合いを求めていた場合、「やはり頑張って無垢材にすればよかった」と後悔する声も聞かれます。
この材質の違いは、家具の価値観を大きく左右するポイントです。(参考:Re:CENO Mag 「無垢材家具と突板家具の違いを学ぼう」)
ウォールナットを選ぶ際は、自宅の床や壁の色、照明との相性を慎重に確認することが成功の鍵です。
家具店で小さなサンプルを見るだけでなく、可能であれば広い面積の天板を見て、自宅に置いた際の具体的なイメージを膨らませることを強くお勧めします。

逆に小さいサイズを後悔をするパターンも

ここまで大きいテーブルの後悔について詳しく解説してきましたが、物事には必ず裏表があります。もちろん、逆に「小さすぎた」と後悔するケースも数多く存在します。
バランスの取れた視点を持つために、小さいテーブルで起こりがちな問題点もしっかりと理解しておきましょう。
小さいテーブルでの後悔で最も頻繁に聞かれるのは、やはり物理的なスペース不足によるストレスです。
例えば、4人家族で一般的な最小サイズとされる幅120cmのテーブルを選んだ場合、普段の食事でさえ一人あたりのスペースが窮屈に感じられることがあります。
特に、大皿料理を中央に並べたり、各自のランチョンマットを敷いたりすると、食器やグラスがひしめき合い、隣の人と肘がぶつかりそうになりながら食事をすることになり、リラックスできるはずの時間が窮屈なものになってしまいます。
また、現代のダイニングテーブルは、もはや食事だけの場所ではありません。
文部科学省が推進する家庭学習の重要性からもわかるように、子供が宿題をする場所として、また大人がリモートワークでパソコンを広げる場所として、多目的に使われることが増えています。
テーブルが小さいと、誰かが作業をしていると食事の準備ができない、食事のたびにパソコンや書類を片付けなければならないなど、用途が著しく制限され、日々の生活に大きな不便を感じることが多くなります。
このように、ダイニングテーブルは大きすぎても小さすぎても日々の不便や後悔につながります。
だからこそ、一時的な憧れや価格だけで判断するのではなく、ご自身の家族構成や現在の、そして将来のライフスタイルを慎重に分析し、「我が家にとって本当にちょうどいいサイズ」を見極めることが何よりも重要なのです。
大きいダイニングテーブルで後悔しないための選び方
- 大きい方がいい?メリット・デメリット
- 150cmは狭い?ダイニングテーブルは大きい?
- 理想的なサイズは?大きいテーブルがおすすめな人、そうでない人
- 大きなダイニングテーブルのある家の実例
- 総括 : ダイニングテーブルが大きいことの後悔を避けるには
大きい方がいい?メリット・デメリット

「ダイニングテーブルは大きい方がいい」という考え方には、確かに多くの魅力的なメリットがあります。
しかし、その裏には見過ごせないデメリットも存在するため、両方を天秤にかけた上で、ご自身の家庭にとってどちらの価値が上回るかを判断することが、後悔しないための最も重要なプロセスとなります。
ここでは、大きいダイニングテーブルがもたらすメリットとデメリットを、具体的なシーンを想定しながら分かりやすく整理しました。
| カテゴリ | メリット(得られる価値) | デメリット(失う可能性のある価値) |
|---|---|---|
| 食事・空間 | 一人あたりの占有スペースが広く、料理をたくさん並べてもゆったりと食事ができる。 友人や親戚が集まった際にも、窮屈な思いをさせることなく余裕をもって対応できる。 | 部屋に物理的・心理的な圧迫感を与え、空間全体が狭く感じられる。 向かい合う人との距離が遠くなり、会話が弾みにくかったり、食事の取り分けが不便になったりする。 |
| 多目的利用 | 食事以外に、仕事の書類やパソコン、子供の勉強道具や趣味の道具を広げても、広々と使える。 複数の人が同時に別々の作業をしやすい。 | サイズが大きすぎることが心理的なハードルとなり、かえって食事専用になりがち。 天板の中央部分などがデッドスペース化しやすい。 |
| 生活動線 | (直接的なメリットは少ない) | 通路を狭め、キッチンやリビングへのスムーズな生活動線を妨げる可能性がある。 椅子を引いた際に壁や他の家具にぶつかり、ストレスの原因となる。 |
| メンテナンス | 天板が広いので、花瓶やオブジェなど、季節感のあるディスプレイを存分に楽しめる。 | 重量があるため移動が極めて困難で、テーブル下の掃除に手間がかかる。 天板を拭き上げる面積が広く、毎日の手入れが負担になる。 |
| インテリア | 存在感があり、LDK空間の主役としてインテリアの核になる。 | 他の家具とのサイズバランスが取りにくく、レイアウトの自由度が著しく低下する。 一度配置すると、模様替えが非常に困難になる。 |
このように、大きいテーブルは「ゆとり」「多機能性」「おもてなし」という大きなメリットがある一方で、「空間の快適性」「日々の利便性」「メンテナンス性」という点でデメリットを抱えています。
ご自身のライフスタイルや住環境が、これらのメリットを最大限に活かせるものか、それともデメリットの影響を大きく受けてしまうものかを冷静に判断しましょう。
150cmは狭い?ダイニングテーブルは大きい?

幅150cmは、日本の住宅事情において4人掛けダイニングテーブルの最もスタンダードなサイズとして広く認識されています。
このサイズ感が「狭い」と感じるか、「大きい」と感じるかは、ご家庭のライフスタイルやテーブルに求める役割によって大きく変わってきます。
150cmが「ちょうどいい」または「大きい」と感じるケース
日常的に3〜4人で「食事」をすることを主目的とするのであれば、幅150cmはほとんどのご家庭にとって十分なスペースを確保できる、非常にバランスの取れたサイズです。
一人ひとりが窮屈さを感じることなく、快適に食事を楽しめます。特に、お子様がまだ小さいご家庭であれば、むしろ「大きい」と感じるくらいのゆとりがあるでしょう。
限られたLDKのスペースを有効活用しつつ、4人家族の基本的なニーズを満たすには最適な選択肢の一つです。
150cmが「狭い」と感じるケース
一方で、ダイニングテーブルに食事以上の役割を求める場合、150cmでは「狭い」と感じる可能性があります。具体的なシーンとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 来客が多いご家庭:友人などを頻繁に招き、5〜6人でテーブルを囲む機会が多い場合、150cmでは少し窮屈に感じられます。補助椅子を使っても、一人あたりのスペースがかなり限られてしまいます。
- 食事と作業を同時に行う場合:家族の誰かが食事をしている横で、別の誰かがパソコン作業や子供の勉強を見る、といった使い方をする場合、互いのスペースが干渉しやすくなります。
- 体格の大きいご家族がいる場合:ご家族の体格によっては、一人あたりに推奨されるスペースよりも広く確保しないと、窮屈に感じるかもしれません。
- デザイン性の高い椅子を使いたい場合:特にアーム(肘掛け)付きの椅子は、一般的な椅子よりも幅を取るため、4脚並べると隣との間隔がかなり狭くなります。
結論として、幅150cmは4人家族の「食事」を基準にすれば非常に優れた定番サイズですが、プラスアルファの「ゆとり」や「多用途性」を重視するなら、少し手狭に感じる可能性がある、と覚えておくと良いでしょう。

理想的なサイズは?大きいテーブルがおすすめな人、そうでない人

ダイニングテーブルの理想的なサイズを導き出すには、「使用人数」と「部屋の広さとのバランス」という2つの重要な軸で考えるのが基本です。
後悔しないためには、まず基本となる「一人分のスペース」の寸法を正確に把握しましょう。
1人あたりに必要なスペースの目安
食事をする際に、1人がストレスなく快適に過ごすために必要とされるスペースは、多くの家具メーカーやインテリアの専門家によると、一般的に「幅60cm × 奥行40cm」が最低限の目安とされています。
これに配膳スペースなどを加味すると、より快適になります。
この基準を基に、一般的な使用人数ごとのおすすめテーブルサイズは以下のようになります。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
| 使用人数 | 推奨されるテーブル幅 | 主な特徴と選び方のポイント |
|---|---|---|
| 1〜2人 | 80〜120cm | コンパクトな空間にも置きやすい基本サイズ。来客を想定するなら、少しゆとりのある120cm幅や伸長式もおすすめ。 |
| 3〜4人 | 135〜160cm | 135cm〜150cmが最も標準的。ゆとりや作業スペースを重視するなら150cm以上が快適。160cmは設置スペースを要確認。 |
| 5〜6人 | 160〜200cm | 160cmあれば5人でもゆったり座れる。日常的に6人で使用する場合は、180cm以上あるとストレスなく使える。 |
| 7人〜 | 200〜 | 大人数での利用が主となるサイズ。LDK全体で25畳以上の広いダイニングスペースが必須。 |
これらのサイズを踏まえた上で、大きいダイニングテーブル(ここでは幅160cm以上を目安とします)の購入を心からおすすめできる人と、一度立ち止まって慎重に検討した方がよいおすすめできない人の具体的な特徴をまとめます。
大きいテーブルが「おすすめできる人」の特徴
- 日常的に5人以上で食事をするご家庭(二世帯住宅など)
- 友人や親戚を招いて、大人数で食卓を囲む機会が頻繁にある
- ダイニングテーブルを食事だけでなく、仕事や子供の勉強など多目的に、かつ同時に使いたい
- LDKが広く、テーブルを置いても十分な生活動線(最低80cm以上)を確保できる
- 将来的に家族が増える明確な予定がある
大きいテーブルを「おすすめできない人」の特徴
- ダイニングスペースが物理的に限られている(10畳未満など)
- 来客は年に数回程度しかなく、そのために普段の利便性を犠牲にしたくない
- テーブルの用途は基本的に食事のみと割り切っている
- 掃除や模様替えの手間をなるべく減らしたいミニマルな暮らしを好む
大きなダイニングテーブルのある家の実例

大きいダイニングテーブルを空間に美しく調和させ、後悔なく活用するためには、実際のレイアウト実例から成功のヒントを得ることが非常に有効です。
成功しているレイアウトには、単に「置く」のではなく、空間全体をデザインする共通の工夫が見られます。
例えば、ある4人暮らしの家庭では、160cm幅の大きなダイニングテーブルをLDKの中心に堂々と配置しています。
このレイアウトが成功している最大のポイントは、テーブルと他の家具、そして壁との間に十分な「呼吸する余白」を確保している点です。
テーブルの周囲には、人がストレスなくスムーズに通り抜けられる100cm以上の動線が確保されており、食事中に誰かが席を立っても、他の家族の邪魔になりません。
「ゾーニング」と「視線の抜け」による圧迫感の軽減
また、リビングエリアとの間に毛足の長いラグを敷くことで、視覚的に「ダイニングスペース」と「リビングスペース」を分ける「ゾーニング」というインテリア手法を取り入れています。
これにより、大きなテーブルが空間全体を曖昧に占領するのを防ぎ、それぞれの空間に役割と落ち着きが生まれています。
さらに、テーブルの奥には大きな窓を配置し、「視線の抜け」を作ることで、物理的な広さ以上に開放感を感じさせる工夫もされています。
空間を広く見せるテクニック
大きなダイニングテーブルを主役にする場合、周囲に置く家具はあえてシンプルで背の低いものを選ぶと、圧迫感が軽減され、バランスの取れた空間になります。
また、片側を椅子ではなく壁付けのベンチにすると、使わない時にすっきりと収まり、動線を確保しやすくなるため、限られたスペースで大きなテーブルを置きたい場合に有効なテクニックです。
このように、大きなダイニングテーブルのある理想の家を実現するには、ただテーブルを置くのではなく、動線の確保、ゾーニング、視線の抜けといった空間全体のコーディネートをセットで考えることが、後悔を避けるための絶対的な秘訣と言えるでしょう。
総括 : ダイニングテーブルが大きいことの後悔を避けるには
これまで見てきたように、ダイニングテーブルが大きすぎることによる後悔は、購入前のいくつかの重要なポイントを事前にチェックすることで、そのリスクを大幅に減らすことができます。
最後に、後悔しないための「究極のチェックリスト」をまとめました。理想の一台に出会うために、ぜひご活用ください。
- 部屋の広さとテーブルサイズのバランスは客観的に見て適切か
- テーブルの周囲に椅子を引いて座り、人が通る動線(最低80cm)は確保できるか
- 日常的に使う人数と、最大で使う人数のどちらを優先するか決めたか
- 食事以外の用途(仕事・勉強・趣味)で使う頻度や広さは十分か
- 数年後の家族構成の変化(子供の成長、同居など)を見越しているか
- 新聞紙などで実物大の型紙を作り、床に置いて圧迫感を確認したか
- 他の家具や床材、壁紙とのデザインや色の調和は取れているか
- テーブルの高さと、今使っている、または購入予定の椅子の高さのバランスは快適か
- 玄関や廊下、階段、エレベーターなど搬入経路の幅と高さをメジャーで実測したか
- テーブルの重量はどのくらいか、掃除や将来の移動は現実的に可能か
- 天板の素材(無垢材・突板・メラミンなど)のメリットとデメリットを理解し納得しているか
- 円形や楕円形、角丸など、長方形以外の形状が部屋に合う可能性も検討したか
- 来客時だけ広げられる伸縮式(伸長式)テーブルという賢い選択肢も考えたか
- 最終的には「少し小さいかな?」と感じるくらいが、日本の住宅では丁度良い場合も多いと心得る
- 一時的な憧れだけでなく、何年にもわたる日々の暮らしに本当に寄り添った選択ができているか